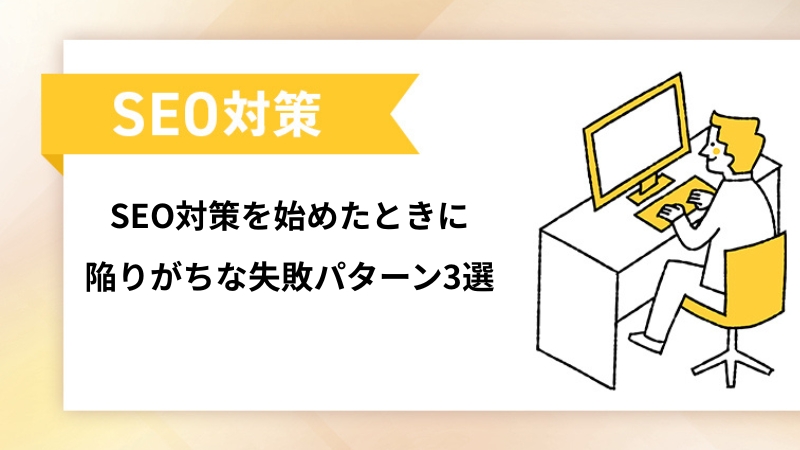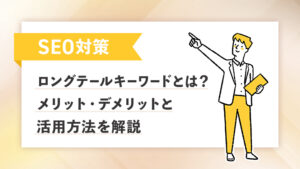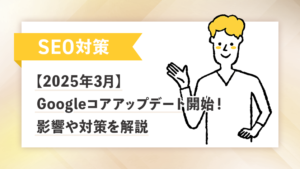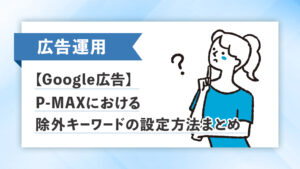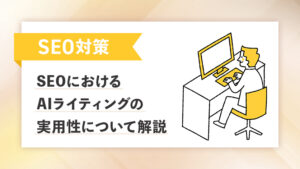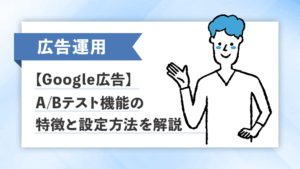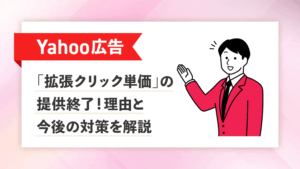「SEO対策を始めたのになかなか成果が出ない」とお悩みの方、必見です。
本記事では、多くの方が陥りがちなSEOの3つの失敗パターンと、その具体的な対策を解説します。
キーワードの正しい扱い方や、上位記事の正しい読み取り方まで紹介するのでぜひ最後までご覧ください。
パターン1:キーワードをとにかく盛り込むべきだと思っている
「検索されやすいようにたくさんキーワードを入れたい!」と思うところですが、SEOの観点からするとあまり有効な手段ではありません。
なぜ不必要に盛り込んではいけないのか、どう盛り込めばいいのかを本章で解説します。
「キーワードスタッフィング」と呼ばれるスパム行為になる
「SEOといえばキーワードが重要!とにかくキーワードをタイトルや文章に盛り込もう」と思っている方は意外と多いのではないでしょうか。
これは「キーワードスタッフィング」と呼ばれる行為でスパムと見做されてしまいます。
キーワードの乱用とは、Google 検索結果のランキングを操作する目的で、ウェブページにキーワードや数字を詰め込むことです。キーワードの乱用では、不自然にリストやグループの形式を使ったり、関連性のない場所でキーワードが記載されたりする傾向があります。
引用:Google「Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー」
スパムと認識された場合、検索順位の下落やインデックスからの削除などペナルティを受ける可能性があるので絶対に避けましょう。
また、Googleからの評価だけでなくユーザー目線で考えても読みづらい記事になり、離脱される原因となってしまいます。
例えばあなたがネットを使って「新宿のカフェ」を探している時に、こんな文章が出てきたらどう思いますか?
新宿でカフェをお探しですか。
この新宿のカフェは、新宿エリアで一番おすすめのカフェです。
新宿にはたくさんのおしゃれなカフェがありますが、このカフェは特におしゃれなカフェとして人気です。
新宿でwifiや電源があるカフェを探しているなら、このカフェがおすすめです。
新宿、カフェ、おすすめ、おしゃれ、wifi、電源。
ぜひ、この新宿のおすすめカフェに来てください。
同じ言葉が繰り返されているため、文章として読みにくく「戻るボタン」を押したくなるのではないでしょうか。
このように「Googleからの評価」「読者からの評価」2つの観点から悪影響なので、キーワードを無理やり詰め込むのは控えましょう。
結局キーワードはどう扱うべき?
「じゃあどうキーワードを盛り込めばいいの?」と思われるかもしれませんが、特殊なことをする必要はありません。
読者が読みやすいように「意味の通る文章の中に自然に盛り込む」ことを意識すればOKです。
SEO対策と聞くと「なにかしらのテクニックで順位を上げる必要がある」と思われがちですが、実際は読者に寄り添うことが最優先。
読者が満足した結果をみて、Googleが評価を下すので最優先は読者であることを押さえておきましょう。
実際に弊社でSEO記事を作成する際も、キーワードを意図的に配置しているのは以下の2箇所のみです。
- 記事のタイトル
- 1章の見出し
実際にGoogleの公開しているベストプラクティスにも以下のような記載があるので、タイトルと1章の見出しには意図的に配置しておくことをおすすめします。
サイトの SEO はさまざまな方法で改善できますが、ウェブ コンテンツの掲載順位や Google 検索での表示に最も影響が大きい対策は次のようなものです。
有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツを作成する。
ユーザーがコンテンツを検索するときに使われる可能性のある単語を選んで、これらの単語をページ上の目立つ場所(ページのタイトル、メインの見出しなど)や、わかりやすい場所(代替テキスト、リンクテキストなど)に配置する。引用:Google「Google 検索の基本事項」
パターン2:文字数はとにかく多い方が良いと思っている
「文字数が多い方がSEOに有利」とお考えの方も多いと思いますが、文字数とSEO評価に直接的な関係はありません。
Google が推奨する文字数があると聞いたり読んだりしたために、特定の文字数に合わせて作成していませんか?(いいえ、そういったものはありません)
引用:Google「有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成」
ですが「でも上位記事は軒並み文字数が多いじゃないか」と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
確かにそのような傾向はありますが、「文字数の多い記事がGoogleから高く評価されている」のではありません。
「Googleから評価が高くなりやすい網羅的なコンテンツを作った結果、文字数が多くなった」のが実際の理由です。
この背景には「読者のニーズ」があるのですが、文字数と順位の関係性については以下の記事で深掘りして解説しているので詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
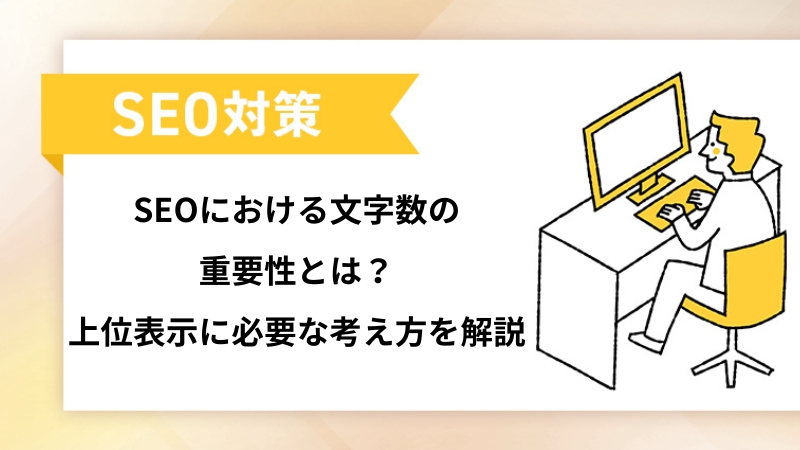
パターン3:上位記事を真似るだけになっている
上位記事を参考に記事を書いている方は多いと思いますが、さらに順位を上げたり流入を増やすならもう一歩踏み込むことをおすすめします。
上位記事を真似るだけではいけない理由と、正しい上位記事の見方を解説します。
上位記事を真似するだけでは順位は上がらない
上位表示されているサイトを参考にするのは重要ですが、ただ真似るだけでは評価されません。
狙うキーワードの上位記事は実際にGoogleから高く評価されている、現時点での「正解」とも言えます。
上位記事の構成から読者のニーズを推測したり、どの程度網羅性が必要になるかも概ね目星を付ける上でチェックすべきです。
ただ、そのまま全く同じ構成、見出しで記事を作成しても多くの場合、元の記事より高く評価されることはありません。
というのも、すでに高く評価されている記事があるのであれば後発の真似た記事を高く評価する必要がないからです。
コンテンツと品質に関する質問
コンテンツが他のソースを参考にしたものである場合は、単なるコピーや書き換えではなく、付加価値とオリジナリティを十分に示すものですか。
引用:Google「有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成」
また、見出しを真似るだけでなく内容自体が酷似している場合、コピーコンテンツとしてペナルティの対象になることもあるので注意しましょう。
上位記事の弱点と独自要素を探そう
上位記事をそのまま真似するのではなく「上位記事がカバーしきれていない情報はないか」「自分だから盛り込める独自の情報はないか」という視点でも構成を見直してみましょう。
例えば「プログラミングスクール おすすめ」というキーワードを狙う場合を考えてみてください。
上位記事を分析すると、多くのサイトが人気スクールのランキングや料金比較を掲載していることが分かります。
どこもスクールへの契約に繋げたいので自然な形と言えるでしょう。
ですが、そこでそのまま真似るのではなく、追加で「30代未経験者」に特化した学習ロードマップや、転職成功のポイントを記載したり、「挫折しやすいポイント」や「受講して後悔した点」などを盛り込むことで上位記事の弱点を補強した記事にできるのです。
また、実際に5社の無料カウンセリングを受けてみて、その対応や内容を比較した独自のレポートを追加するのも良いでしょう。
このようにただ真似るのではなく、プラスワンの情報を意識して執筆することをおすすめします。
まとめ
SEO対策で陥りがちな3つの失敗パターンを解説してきました。
キーワードの量、文字数、上位記事の真似などGoogleの評価を重視しすぎるあまり、肝心の「読者」を意識していないことが主な原因です。
まずは読者の視点に立って、コンテンツを作成することを意識してみましょう。