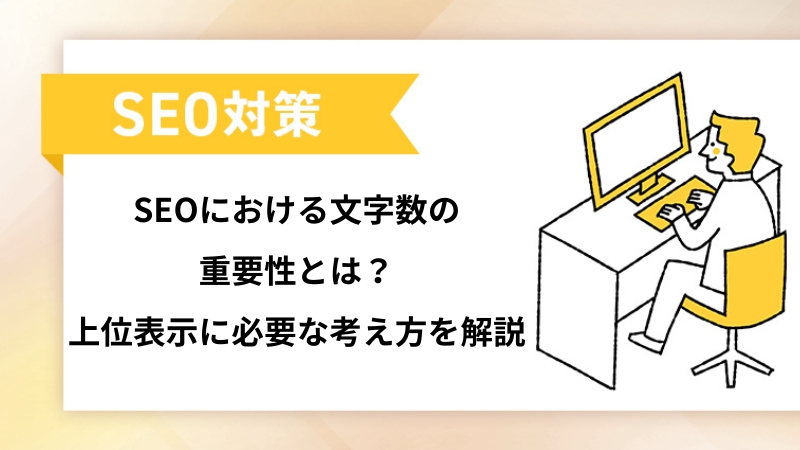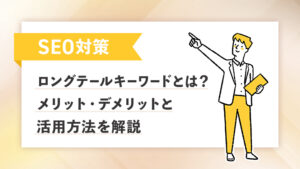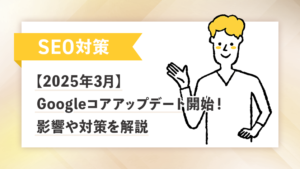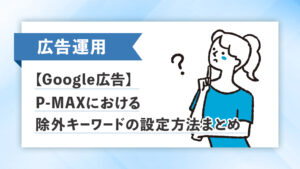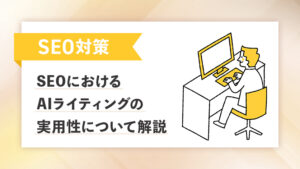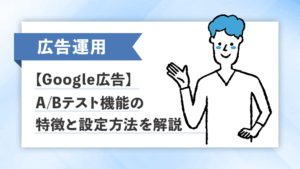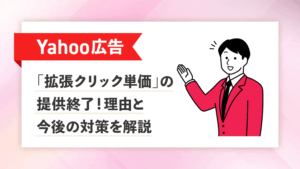記事を作成する際「SEOのためには何文字くらい書けば良いのだろうか」と悩んだ経験はありませんか。
結論として、SEOと文字数に直接的な関係はありませんが、上位表示される記事は結果的に文字数が多くなる傾向にあります。
今回の記事では、Googleの公式見解を基にSEOと文字数の関係性について詳しく解説。
さらに「なぜ上位表示される記事は文字数が多くなるのか」「文字数以外でGoogleから評価される記事はどう作ればいいのか」も深掘りしてご紹介します。
ぜひ最後までご覧ください。
1. 文字数に関するGoogleの見解
Googleは「文字数」そのものを検索順位の評価指標にはしていないと公式に明言しています。
Google検索セントラルの公式ドキュメント「有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツの作成」の中でも、文字数に関する考え方が明確に示されています。
Google が推奨する文字数があると聞いたり読んだりしたために、特定の文字数に合わせて作成していませんか?(いいえ、そういったものはありません)
この一文が意味するのは「単に文字数が多い、あるいは少ないというだけでGoogleからの評価が直接的に上下することはない」ということです。
例えば品質が低く、読者の役に立たない内容で文字数だけを増やしても評価は上がりません。
その一方で、短い文章であってもユーザーが検索したキーワードの意図に対して完璧な答えを提供できているのであれば、良質な記事として評価されます。
実際に弊社でも、あるメディアの3000字台の記事群と4000文字台の記事群、それぞれの平均順位に差異があるかを調査しましたが、大きな差は見られませんでした。
つまり、Googleが本当に重視しているのは文字数という表面的な指標ではなく、あくまでコンテンツの「品質」であり、それは「ユーザーの検索意図にどれだけ合致しているか」という本質的な部分と言えるでしょう。
2. 文字数が多いとSEOで評価されやすい2つの理由
Googleが「文字数はランキングに影響しない」と明言しているものの、上位を獲得している競合の記事を見ていると5000〜10000文字の記事が多い気がしませんか?
確かにGoogleは文字数そのものを順位の基準にしていませんが、文字数の影響を受けやすい2つの基準があります。
- ユーザーの検索意図を網羅できているか
- E-E-A-Tが高いか
2つの基準の詳細を解説します。
2-1. 理由①:ユーザーの検索意図を網羅すると、自然と文字数は増える
上位表示される記事の文字数が多くなる最大の理由は、ユーザーが知りたい情報を網羅して提供しようとすると結果的に多くの情報量が必要になるからです。
ユーザーが検索エンジンにキーワードを打ち込む際の目的、いわゆる「検索意図」は一つだけではありません。
例えば、「SEO 始め方」と検索するユーザーを想像してみてください。
このユーザーは「具体的な手順を知りたい」という明確な目的(顕在ニーズ)だけでなく「費用はどのくらいかかるのか」「効果が出るまでどれくらいの期間が必要か」「初心者が陥りがちな注意点はないか」といった、まだ自覚していない潜在的な疑問(潜在ニーズ)も抱えている可能性が非常に高いです。
そんな潜在ニーズまで含めて丁寧に解説し「網羅性」を高めたコンテンツは、ユーザーがページを離脱することなく、長時間滞在し、その記事だけで疑問を解決できるため、Googleからの評価も高くなりやすい傾向があります。
つまり「文字数が多いからGoogleの評価が高まる」のではなく「Googleから評価が高くなりやすい網羅的なコンテンツを作った結果、文字数が多くなった」ということです。
したがって、コンテンツを作成する際には「何文字書くか」ではなく、「読者の疑問を解決するために、どんな情報が必要か」という視点で考えるようにしましょう。
2-2. 理由②:E-E-A-Tを示すには情報量が必要になる
E-E-A-Tは(経験・専門性・権威性・信頼性)の頭文字「Experience(経験)」「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」の略でGoogleが定める評価基準の1つです。
このE-E-A-Tを少ない文字数で示すのは容易ではありません。
例えば「最新のスマートフォン」に関するレビュー記事を書くとします。
単に「このスマホはカメラがきれいです」と一言書くだけでは、読者はその情報を信用できません。
「実際に1ヶ月使ってみて、夜景モードで撮影した写真と日中モードの写真を比較した結果、ノイズの少なさにこれだけの差があった」という自身の経験や「旧モデルや同価格帯のスマホと比較して、センサーサイズがこれだけ大きく、処理チップの性能がこれだけ高い」といった専門的な知識を盛り込む必要があります。
なので、やはり「文字数が多いからGoogleの評価が高まる」のではなく「Googleの評価基準であるE-E-A-Tを示すことのできる記事を書いた結果、文字数が増えた」となります。
文字数の多さよりも、コンテンツに独自の経験や専門知識に基づいた情報があるかを意識してみましょう。
3. Googleから評価される記事を作る上で重要な2つのコツ
SEOにおいて重要なのは文字数ではなく、その背景にある「網羅性」や「E-E-A-T」であることを解説してきました。
では、具体的にどうすれば文字数に囚われずに質の高いコンテンツを作成できるのでしょうか。
この章では、実践的な2つのコツをご紹介します。
3-1. 競合サイトを分析し、必要な情報量を把握する
上位記事の文字数ではなく、構成に注目しましょう。
狙っているキーワードで検索し、1位から10位までの記事で扱っている内容を洗い出すことで、そのキーワードにおける「読者の検索意図」が何であるかを把握することができます。
「読者の検索意図」を十分に満たせる構成でない場合、文字数が多くても上位表示は難しくなるのでここで入念にリサーチします。
弊社ではAhrefsを使用することが多いものの、ラッコキーワードなどの無料ツールでも上位記事の構成は十分チェックできます。
記事の構成を作る際はツールを活用しながら、必要な文字数ではなく「必要な情報量」を意識して上位記事をチェックしてみましょう。
3-2. 検索意図を深く掘り下げ、独自の要素を追加する
上位記事の分析で把握した「読者の検索意図」に加え、他の記事にはない「独自の要素」を盛り込むことが、Googleからの高評価を得るためには欠かせません。
競合サイトと同じような情報だけを並べても、読者から「情報が薄い」と思われて、網羅性を高めてもすぐに離脱されてしまいます。
ここで重要になるのが先述したE-E-A-Tです。
リアルな体験談や自社で実施したアンケート、過去の事例など自分のサイトならではの情報を加えていきましょう。
また、専門家目線での独自の意見を掲載するのも専門性が増すのでおすすめです。
こうした独自の情報を盛り込んでいくと結果的に文字数が増えていきますが、評価されているのは「情報の質と深さ」であることを押さえておきましょう。
まとめ
SEOにおける文字数は、検索順位を直接決める要因ではありません。
しかし、Googleに評価される質の高いコンテンツを作成しようとすると、結果的に文字数が多くなる傾向にあります。
これはユーザーの検索意図を完全に満たす「網羅性」や「E-E-A-T」を盛り込むと、必然的に多くの情報量が必要になるためです。
一見、文字数が増えるので錯覚しやすいのですが、Googleが評価しているのはあくまで記事の「質」と「網羅性」、そして「深さ」です。
文字数が多くなるのはそれらを重視した結果に過ぎないということを押さえておきましょう。